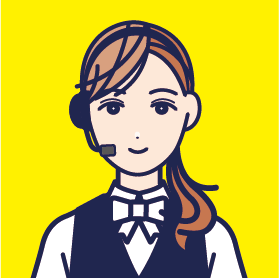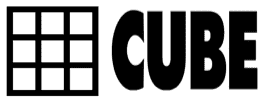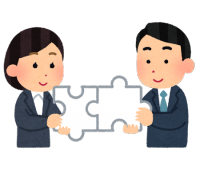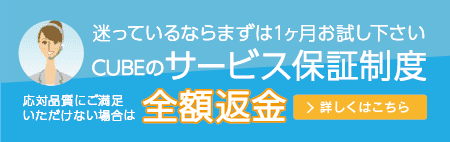【目次】
自信を持つ
クロージングで苦労をしている人は多い。言うまでもなく、クロージングとは ビジネスや営業活動において、顧客と契約を締結することを意味する。もっとざっくばらんに言うと、顧客への最後の一言「買ってください」をいかに効果的に言うかだ。これがなかなか難しい。もともと営業出身でない私は今もそれで苦労をしている。しかし、試行錯誤する中で分かってきたこともある。今回は決して営業の専門家でもない私だが、その中で考えてきたことを専門家の話も交えながら紹介したいと思った。
なぜなかなか「買ってください」と言えないのだろうか。それは突き詰めて考えると、自分が売ろうとしている商品やサービスに自信が持てていないからではないだろうか。果たしてこれを読んでいただいている何人が「そんなことはない」と言い切れるだろうか。「自信を持つ」というのは、「強引に顧客を説得できる」ということではない。「絶対にこれを買っていただいて、顧客に損にならない。今、顧客のためにこれが必要なものだ」と思える自信のことだ。そのために必要なのは、売ろうとしている商品やサービスの知識だけでなく、顧客が持つ問題、課題への理解が欠かせない。
商品知識は絶対か
私が今になって思うのは、仕事を自分で始めた当初、足りなかったのはまずこの商品(私の場合、サービスなのだが)知識だった。「えっ」と驚かれるかもしれないが、自分が売ろうとしている商品がどういうものかぐらいは当然言えても、それが業界や今の激しい技術の変革の中でどういう位置付けにあるのかということが分かっていなかった。競合他社のことや、顧客の課題解決のためにそれをベストなものにするための提案が不足していた。このため、自分が売り込む時の言葉を「より洗練されたものにする」訓練はできても、顧客からの質問を受けることについてどこかごまかしがあったり、なるべくそれを避けようとしていたのだと思う。
そうした商品に対する「絶対的な自信」無くしては、後にどのような顧客のやりとりのノウハウを学んだところで、まったく役に立たないのはいうまでもない。つまり、自分が売ろうとしているものに自信を持つことができない間は、どんなテクニックを使ってもそれは「売れない」のだ。では、売る商品が決まっている生命・火災保険のような場合はどうすればいいか。無責任な言い方になるかもしれないが、やはり自分が売ろうとしている会社が強い保険と弱い保険を知り、弱い保険の部分を補う方法を考えることだろう。

自然な笑顔ができているか
話を急いで悪いが、商品に自信が持てたとしても、それを説明するための顧客への最初のアプローチがきっちりできていない人も多い。商品を売り込むにはまず自分を売り込む必要があることに気づいていない。自己紹介をするにも、笑顔の一つも無ければ、顧客はその営業マンに対して「安心・安全」を感じることができない。「この人なら大丈夫」と思えなければ、どんなに良い話も信じてはもらえない。「人は0.5秒で印象が決まる」とも言われる。ということは、それまでに好意的な印象を与えるための「笑顔」は必須だ。「そんなことは知っている」という人は多いが、それができているかどうかは別だ。
そして、最初のアプローチができれば、次に顧客の抱える悩み、問題について聞き出さねばならない。なぜなら、悩みや問題を解決できるものでないものは、どんなモノでも買う必要は起こらないからだ。これを聞き出すことを急ぐ営業マンは多いが、顧客の心が開いていない内は決してそれを自発的に打ち明けたりしない。見ず知らずの人にいきなり「悩みは何ですか」と聞かれて、自分の弱みをさらけ出すような不用意な人はいない。だから、顧客の欲求や希望から聞いていくのだ。「どんな風になりたいですか」と。そして、現状とのギャップを認識してもらう。
迷っている顧客への対応が腕の見せ所
これはつまり、現状のままだったら顧客に様々な問題が残っている状態で、そのために発生する「損失」を回避させるという心理を利用するのに他ならない。だから、その前にする理想のイメージが大きく膨らめば膨らむほど効果は増すことになる。ここがうまく構築できない間は、これを何度も繰り返すことになる。そしてそれを顧客にしっかりと認識させるのだ。それでも、その流れで「買う」と決める顧客はわずか3%程度でしかないという。17%ほどはその段階で買うのに否定的な反応を示すとされており、それらを除くと残り60%。その顧客をどれだけ買う方に振り向かせるかが営業マンの腕の見せ所となる。
後は営業のテクニックがものを言う。顧客からは、「それでもやはり価格が高い」という不満が残っているのかもしれない。その際も決してむきになって反論することは避けた方が良い。顧客が障壁と感じていることは、なぜそれが障壁になっているのか顧客に聞くことだ。「どうして高いと思うのですか」「どうして今は買うのをやめようと思うのですか」と。そして「じゃあ、いくらぐらいなら適当と思われますか」という問いに対して、何らかの回答があれば、現実の価格とのギャップに対して新たな提案ができるかもしれない。そのやりとりには、ある程度経験も必要かもしれない。