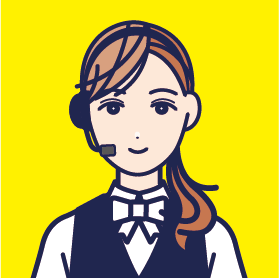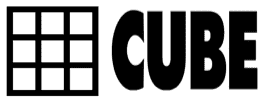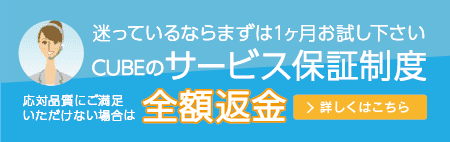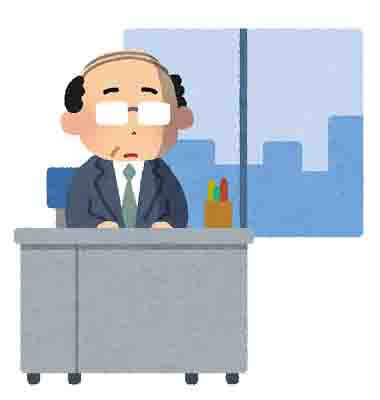
【目次】
進む人材の流動化
好業績下であっても人員削減を打ち出す企業が増えているという。2019年に早期・希望退職を実施した上場企業35社のうち、最終損益が黒字だった企業が約6割を占めたそうだ。これらの企業の削減人員は中高年を中心に合計9000人超と前年の約3倍に増えた。企業は若手社員への給与の再配分やデジタル時代に即した人材確保を迫られているという。このため業績が堅調で雇用環境もいいうちに人員構成を見直そうという動きらしい。
このことを中小・零細企業の側からはどう見ればいいだろう。人材の流動化が進んでいいと歓迎する向きもあろう。事実、大企業で勤めていた中高年が、その後求められて中小・零細企業で働く例は珍しくなくなっている。しかし、中小・零細企業であっても置かれている状況は大企業と同じかそれ以上に厳しいのが当たり前だ。大企業と同じ考えで見れば、採用するなら中高年より若手人材が欲しいという要望が本音であるのではないだろうか。そんな風に考えると、中高年はやっぱり諸手を挙げて歓迎される人材ではないということになってしまう。これはどう考えてもおかしい。「人生100年」といわれる時代にあって、企業は人材に対する考え方を再検討する必要があるように思う。

育てるのに失敗した人材
「企業は人なり」といわれる。そのことに反対する人はいないだろう。しかし、これを企業の成長が第一とする視点から見ると、人材次第で企業の成長が決まるものの見方とは、実際の行動が異なってくる。特に戦後裸一貫で企業を興し、苦労してきた経営者になると、お金をモノに対する所有欲・支配欲が強い方も多く、時には従業員まで企業の所有物と考えるような言動をとることも多いように見られている。所有物である以上、企業の都合でどう扱おうともそれは勝手ということになりがちだ。
実際、今は特にバブル世代の中高年層の人数が多く、年功制の名残で非管理職であっても給料が高止まりしていることが多い。ITに弱いなどビジネススキルの面で時代についていけない人、昇進が頭打ちで仕事への意欲が見られない人も多いのもよくある話だ。個々の事情を見てみるとリストラの対象になっても仕方ないと思われることも多いが、これも見方を変えれば、企業がそれまで人を活かさず放置してきた結果である。「減らす」ということは、これまで雇ってきたもののを価値ある人材として育てておらず、活かすこともせず、これから活用できる見込みもないということを内外に認めているに等しい。

雇用を守った名経営者たち
経営の神様とうたわれている松下幸之助氏は、かつて世界恐慌時にあっても人員削減をせずに乗り切った。「生産は半分。工場は勤務も半日。給与は全額支払う。その代わり休日返上で在庫を売るんや」と従業員に呼びかけたという逸話を残している。現代でも、奥田碩トヨタ自動車元会長は「経営者よ、クビ切りするなら切腹せよ」と述べている。永守重信日本電産会長もこれまでに「雇用は守る。リーマンショック時も誰も切らずに平均5%の賃金カットをして、その後利子を付けて返した」「(ハードワークより)リストラをする方がよほどブラックではないか」と話している。岩田聡任天堂元社長は2期連続で営業赤字を出した2013年6月の株主総会で、リストラを迫る株主に「社員が不安におびえながら作ったソフトは人の心を動かさない」と返答し、雇用を守り抜いた。
本来価値のある人材であれば削減する必要もないはずだ。これらの名経営者が教えてくれるのは、普段から価値ある人材を育てているかということだ。コスト削減のための人員削減はどんな詭弁を弄しても経営の失敗を物語るものであり、あくまでも最終手段で、かつ最悪の手段であることを経営者はもっと心に銘じるべきではないだろうか。
経営者は「良識」を堅持しよう
肝心なのは、ただ漫然と雇い続けることではない。中高年を雇っていても成果が出ないからといって、そのまま腐らせてしまうのは経営の不作為だ。能力の再開発や配置転換などを通じて、個々の従業員が活躍できるようにすることが大切だ。成果が出ないのは、個々人に問題があるのでなく、現在の環境下で成果を上げられないだけと考えるのが経営だろう。それができないのなら、むしろ他の企業を探すように促し、場合によっては転職を支援するのが本当の意味での人を尊重する姿勢といえるのではないか。
「グローバル経営」を掲げる大企業が、周囲でリストラが珍しくなくなっているのを奇貨とし、むしろ「終身雇用」を維持することが時代遅れであるかのごとく競い合うように人員削減を繰り返す現状は、経営者としての「良識」を失くし、自らの責任まで放棄しているように映る。そんな時代だからこそ、むしろ中小・零細企業は逆に経営に小回りの効く特徴を活かし、今後益々人材の流動化が進んでいきそうな時代の中で、人を大切にする経営を貫いていってもらいたいと思う。ここに大企業に勝てる一つの経営があるのではないだろうか。