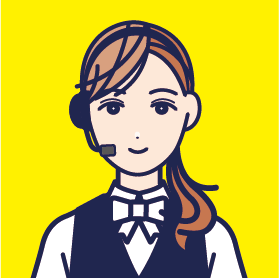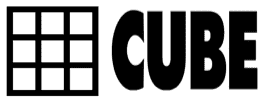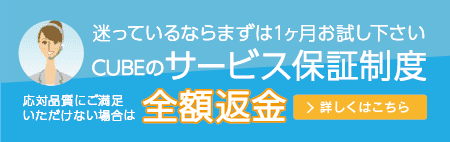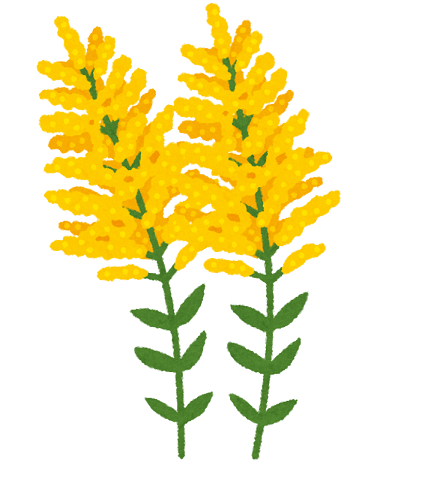
【目次】
変化がもたらすもの
私の隣の家は植物が好きな家族のようで、門の前にはいつも季節の花が植わった鉢が並んでいる。その顔ぶれは季節によって変わるが、ずっと毎年咲き続けているものもある。私は寡聞にしてその一つ一つの名を知らないが、それを見ていると植物の強さを思う。
一般に変化が大きく不安定な環境はけっして植物の生育に適した条件とは言えないとされる。しかし、人間と同様、弱者にとっては複雑で変化の大きいことはチャンスだ。
例えば、私は高校野球をよく見るが、風もなく晴れ渡って、最高のコンディションの状態でプレーができる時、プレーする選手もそれも見る観客も気分が良いに違いない。しかし、こんな最高の条件の時には、全国から選りすぐられた選手を集めたチームと、地元の生え抜きで戦っている公立高校のチームとでは力の差は歴然で、厳しい見方をすれば10回試合をしたとしても、公立学校のチームが勝つことはほぼない。恵まれた環境では両者が実力を発揮でき、そうだとすれば「実力通り」強いものが勝つのだ。
しかし、風も強く、大雨が降った直後だったりしたらどうだろう。こんな状態では誰も野球をやりたいとは思わないが、これだと弱いチームでもひょっとしたら、勝つことはできなくても引き分けぐらいには持って行けるかもしれない。

ニッチを求めてチャンスを活かす
植物も同じである。変化がなく平穏な環境下では、激しい生存競争が起きる。その結果、強い者が生き残り、弱い者が滅びる。そして、生息できる生物の数も少なくなることが分かっている。一方、ある程度環境が変化する条件の下では、多くのニッチが生まれ、激しい競争社会では生き残れなかった弱い植物も、生存の場を得ることができるのだという。つまり、弱者にとって変化の大きいことはチャンスなのだ。
ビジネスでも小さなニッチに力を集中させれば勝てることは分かっている。しかし、様々な企業がそのニッチを奪い合って競っている。ということは、どんなに小さなニッチを求めても、強い企業がそのニッチを奪ってしまうのではないかとすぐに考え着く。
残念ながら、地球上には長い生物の歴史の中で、すでにほとんどのニッチは埋め尽くされているという。だから、もし新たなニッチを手に入れようとすれば、結局競争して他の生物からニッチを奪い取るしか方法はない。しかし、それぞれのニッチではそこに生きる生物が圧倒的なナンバー1を誇っているから新たなニッチを奪うことは容易なことではない。ただひとつ、洪水や山火事といった生物にとって脅威となる大きな変化が起きた時などが、それこそそこに新たなチャンスが生まれた時になる。
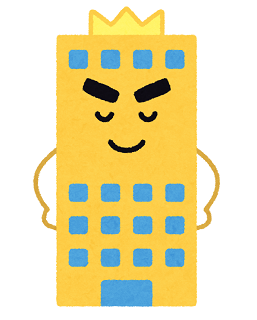
ナンバー1とは「誰にもできない」こと
植物にとって新しくできた環境は、決して強者がすぐには入り込めないニッチであったりするという。環境が破壊された不毛な土地は土の表面が露出しているため乾燥しやすく、栄養分も少なく土地が痩せていることが多いのだ。強者たる植物もそんな環境では実力を発揮することはできない。それこそが、弱い植物である小さな雑草の生存のチャンスの場になる。しかし、そんな不毛な土地もやがて豊かになるにつれ、次々に力の強い植物が入ってきてやがて追いやられるのだという。
つまり、すべての植物はその生育する場でナンバー1なのだ。ナンバー1になれる場所がニッチなのだ。そしてそのニッチを拡大していくのが強者の戦略なのだと分かる。ビジネスでよく引用されるランチェスター戦略でも、強者とは市場占有率ナンバー1を指している。ナンバー1以外のものはすべて弱者なのだ。その厳しさは植物の仕組みとも一致する。ナンバー1しか生き残れない。しかし。ナンバー1になるチャンスはいたるところにある。そして植物を見ていると、ナンバー1とは「誰にも負けない」というより、「誰にもできない」ことを指すことを教えてくれる。
100年に一度の大変革期
ビジネスの世界では今は「100年に一度の大変革期」にあると言われる。大企業であっても生き残りを賭けて必死に挑戦を続けている。大企業でさえそうであるのに、それに規模で劣る企業がその変化の波を捉えられなければ、一体どこで生き残るというのだろう。今は目先、仕事が詰まっていて忙しいという経営者は多い。それを口実にして、今のうちに生き残りのための手を打たねばならないのに、それを見逃している経営者の何と多いことか。変化を恐れていては生き残れないが、それは変化に目を閉じていても同じことだ。
じゃあ、何をすれば良いのかとよく聞かれるが、それこそ自分で考えるべきことだ。ただひとつ言えることがあるとすれば、よく経営の大切な要素に「ヒト、モノ、カネ、情報」と言われ、「ヒト、モノ、カネ」にはそれぞれ対応しても、「情報」に取り組む企業はまだまだ少ないように感じている。情報といっても様々な点からの取り組みが考えられるが、まず取り組みやすいところから言うと、それぞれの企業の強みを情報発信するところから始めるように勧めている。そこから自ずと方向性も見えてくるのではないだろうか。